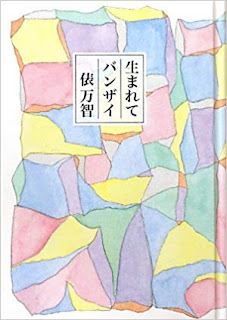秋山 開
目次
ぼくは大学で労働法を専攻していたんだけれど、ちょうどそのころ「オランダではワークシェアリングが導入されている。これを日本にも!」という話をよく聞いた。
日本は不況のまっただなかで終身雇用の崩壊だとか派遣切りだとかが話題になっていたころだったから、これぞ今後の働き方!と思ったものだ。
それから十数年。ワークシェアリングなんてとんと聞かなくなった。
その間、日本では高齢化がさらに進み、若手の数は減り、女性の社会進出は進んだ。ワークシェアリングを必要とする労働者は前よりも増えているはず。しかし働き方改革だなんだと呼び声の勇ましさとは対照的に、働き方はまったく多様化していない。
正社員で働くなら残業もセット。派遣社員だと二年で契約切れ。パートタイマーでは食っていけない。
たとえばシングルマザーの「保育園の送り迎えがあるから長くは働けないけど子どもを養えるぐらいは稼がないといけない」なんて要望は実現不可能というのが日本の現状だ。決して贅沢を言ってるわけではないのに。
だがオランダでは多種多様な働き方が認められているという。
このようにオランダでは、30年以上もの間、働き方の改革が進められてきました。その結果、男性であろうと女性であろうと関係なく、「どういうふうに働きたいのか」「どれくらい働きたいのか」「どこで働きたいのか」を自ら決めることができるようになったのです(もちろん職業によって制限はありますが)。
「夫は正社員として家計を支えて会社の命令なら残業でも転勤でもおこない、妻は専業主婦として家事と育児に専念」
なんてのは戦後数十年のごく短期的な”常識”だったのに(当時ですら幻想に近かったと思うが)、いまだにその例外的な”常識”に基づいた制度がまかりとおっている。
ぼくは以前どブラック企業に勤めていた。年間休日は約八十日。月に百時間を超えるサービス残業。インフルエンザでも休めない。
その会社は結婚を機に辞めた(そしてほどなくして潰れた)。「生活できない」と思ったからだ。
次の会社はいくぶんマシだったが、やはり月に八十時間ぐらいの残業があり、幼い子どもがいても飲み会や社員旅行は強制参加だった。
そして今は、残業は月に一時間程度(つまりほぼゼロ)。強制参加の飲み会もない。
子どもを保育園に送ってから出社し、帰ってから子どもといっしょに晩ごはんを食べ、子どもといっしょに風呂に入り、子どもといっしょに寝る。すごく幸せな暮らしだ。
これが誰にとってもあたりまえになればいい(仕事をしたい人はすればいいけど)。
「給料はそこそこでいいから残業ゼロがいい」という人は多いはずなのに、そんなごくごく控えめな希望ですらなかなか叶えられない。
そんなにむずかしいことじゃないはずなのに。
五人で食事をするのに椅子が四つしかない。どうすればいいか、答えはかんたんだ。
なのに「席が足りないからひとつの椅子にふたりで座ろう」とか「交代で立ちながら食事をしよう」とかやってるのが日本の企業だ。それを毎日くりかえしている。そして、食いづらいとか食うのが遅いとか文句を言ってる。
席が足りないなら椅子を増やせばいい。人手が足りないなら人を増やせばいい。
解決策はいたってシンプルだ。
『18時に帰る』には、さまざまな働き方のケースが紹介されている。
短時間勤務、週四日勤務、テレワークなど。
兼業主婦はもちろん、男性正社員、さらには管理職や経営者までもが家庭の事情にあわせて短時間勤務を選んでいる。
これを支えているのは、ただひとつのシンプルな原則だ。
これは、今から約20年前の1996年に労働時間差別禁止法(Wet onderscheid arbeidsduur)によって定められたもので、同法によってフルタイムワーカーとパートタイムワーカーの待遇格差が禁止されました。
日本では「同一労働同一賃金にしよう!」なんて叫ばれているけど、オランダはその先をいっていて、”同一労働同一条件”が実現されている。短時間勤務であっても時間あたりの賃金を同じにするのは当然で、雇用形態や福利厚生も同じ権利が認められるのだ。
この原則が徹底されているから、「出産のタイミングで休職する」「子どもが小さいうちは出勤時間を減らす」「親の介護があるから時短勤務する」といった選択が可能だし、なにより子育てが終わったら
以前と同じ条件で復帰できる というのが大きい。
日本の働き方だと、「子どもが小さくてもフルタイムで働きつづける」か「パートにして、子育て期間だけでなくその先のキャリアも諦める」の二択しかない場合が多い。
”同一労働同一条件”を実現させないと、やれ働き改革だ一億総活躍社会だと声高に旗を振っても何の意味もない 。
国会でやるべきことはただひとつ、オランダと同じように労働時間差別禁止法を成立させること。政治家の旦那様連中である経団連の言うことなんか無視して。かんたんでしょ?
もちろんオランダにはオランダの問題があるのだろう。
この本には「オランダの働き方はこんなにすばらしい!」という話しか出てこないが、不満を抱えている人だって当然いるだろう。
(ちなみに”同一労働同一条件”を実現させた後のオランダの経済成長率は、世界的に見ても高い水準を維持している。多様な働き方を選べるようにすることは少なくとも経済的にマイナスにならないようだ)
とはいえ、選択肢を多くすることはまちがいなく労働者にとってよいことだ。
そしてそれは、企業にとってもプラスになる。
ユトレヒト大学のプランテンガ教授の会話に、とても印象的な話がありました。それは次のような内容です。「働くことに幸せを感じている従業員を増やすことが、企業の生産性を高めるのです。
前述した、ぼくが勤めていたブラック企業ではどんどん人が辞めていっていた。
たくさん辞めてたくさん採る。求人サイトには常に求人が載っていて、人材紹介会社にも年間何千万という紹介料を払っていた。
社員が辞めるたびに引継ぎコストが発生するし、個人が持っていたノウハウは失われる。
なんて無駄なんだ、新規採用に使う金を、今いる社員を辞めさせないために使えよとずっと思っていた。
だがブラック企業の経営者というのは、合理的な考えが嫌いなのだ。どちらが本当にお得か、なんてことは気にしていない。とにかく「自分が苦労したのに自分のところの社員が苦労していないのが気に入らない」の一心でブラック化に磨きをかけているのだ。
だからどれだけ儲けようと社員には分配しない。待遇も良くしない。
こういう会社がのさばってきたのが日本社会だ。
しかし風向きは変わりつつある。労働者人口が増えつづけていた時代は終わった。若い人はどんどん減ってゆく。不況になったとしても、昔ほど若者が就職に困ることはない。
労働者の立場が相対的に強くなり、労働者が企業を選べるようになってゆく。
こうした流れについていけない会社はどれだけ利益率が高かろうが、人がいなくなってつぶれる。
これからは「社員が辞めない会社」だけが生き残っていく時代になるのだ。
ぼくは経営者ではないが、幸いなことにある程度なら社員の働き方を決められる立場にある。
オランダ式の自由な働き方を導入してみようと思う。
その他の読書感想文は
こちら