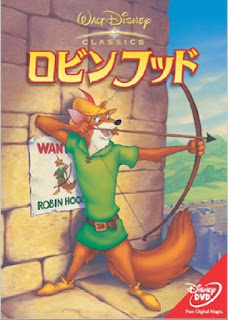レイチェル・シモンズ(著) 鈴木 淑美(訳)
小学四年生の娘が、人間関係のトラブルに巻き込まれた。
同じクラスの女の子三人と仲良くなり、何をするにも四人一組だった。だがその中のSという子が「○○を無視しよう」などと言い出し、S以外の三人が順番に無視されるようになった。さらにSがある子の持ち物を隠してその子が泣いたことで、教師の知るところとなった。
うちの子は積極的に加担していたわけではないようだが、Sに言われるまま無視に協力したりしていたので(娘が無視されることもあったようだ)、親が教師から学校に呼び出される事態となった。
教師や娘からいろいろ話を聞くかぎり、Sはなかなかの問題児のようだ。他の子の持ち物を盗ったり、しょっちゅう嘘をついたり。さらにいじめが発覚して教師から怒られた後も、教師の前でだけ反省するふりをしているがまったく反省せず、懲りずにいじめていた相手にわざとぶつかったりしているらしい。
さらにSの母親もなかなかアレな人で、いじめ発覚後に会って話す機会があったのだが、「なんか先生が言ってることおかしいとおもうんですよね。うちの子が嘘をついてると決めつけてて」などと言っていた。子どもなんて嘘をつく生き物だろう、自分の子の言うことを全面的に信じられるほうがおかしいだろ、とおもったのだが「はあ、そうですか」と適当に相づちを打っておいた。子が子なら親も親だ。
ま、それはよくある話だ。どこにだっておかしなやつはいる。いじめがない学校なんてほとんどないだろう。
ぼくが理解できないのが、そんなことがあっても娘がSとの付き合いを断ちたがらなかったことだった。聞くと、いじめ発覚後、いじめられた子はもちろん、他の子もSとは距離をとっているようだ。「親からSちゃんと遊ばないように言われたから」とはっきり宣言した子もいるという。
そこまではしないにしても、ぼくも娘にはSと距離を置いてほしいとおもう。ものを盗んだり、いじめがばれてもすぐにくりかえすような子は、そう簡単に改心しないだろう。今後もトラブルを起こす可能性が高い。
なのに娘は「みんなが離れていったらSちゃんがひとりになっちゃうから」などと変な優しさを見せていた。いじめや盗みをして孤立するのは自業自得じゃないか、そんなやつに優しくしてもつけあがることはあっても改心することはないぞ、とおもうのだけど。
ぼくは昔から「嫌なやつがどんなにひどい目にあってもざまあみろとしかおもわない」薄情な人間なので、嫌な目に遭ってもつきあいを断とうとしない娘の気持ちが理解できない。
ということで2002年にアメリカで刊行されて話題になったという『女の子どうしって、ややこしい!』を読んでみた。数々のインタビューをもとに、女の子同士のいじめのパターンを明らかにした本だ。
掲載されているのはアメリカのケースばかりだけど、たぶん日本の場合も大きくは変わらないだろう。傾向として、女子のいじめは明らかに男子のそれとは異なる。
男子のいじめが友だちの外のメンバーに対して向かうのに対し、女子のいじめは仲良しグループ内で起こる。
男子のいじめは強者が弱者を虐げる構造なのに対し、女子はいじめる子といじめられる子が頻繁に入れ替わる。
女子のいじめは教師や親の目につきにくく、暴力やはっきりとした暴言を伴わないことも多いので、なかなか明るみに出ない。
かんたんにいえば、女子のいじめのほうが複雑で巧妙ということだ。ばれにくいし、誰が見ても悪い暴力や暴言ではなく「冷たくする」「仲間に入れない」「気づかなかったふりをする」「ときには優しくする」など、一筋縄ではいかない方法をとる。
著者はこれらの行動を、男子がよくやるあからさまないじめに対して「裏攻撃」と呼ぶ。
男子の暴力は、ある程度は許容されることが多い。「弱い者いじめはダメ」「無抵抗の相手を攻撃してはいけない」といったルールはあるが、「強くてまちがっている者に暴力で立ち向かう」「やられたからやりかえす」「誰かを守るために闘う」などはむしろ善しとされることも多い。「男の子はちょっとぐらいやんちゃなほうがいい」という価値観は今も根強く残っている。
一方で女子の暴力や暴言は許されにくい。「女の子なんだからおしとやかにしなさい」と言う人は今では減ったが、それでも女子の暴力や暴言は男子のそれより厳しくとがめられる。
その結果、抑圧された女子の攻撃は巧妙で間接的なものとなる。
女の子のいじめ、親や教師が気づきにくいし、気づいたとしてもやめさせにくい。
こういういじめには、親や教師が介入しにくい。暴力をふるっていたら教師はすぐにやめさせるが、「あの子と仲良くしなさい!」と交友を強制することはできない(仮に強制したとしても仲間はずれにされていた子は救われないだろう)。友だちに対して秘密を持つな、とも言えない。
ただ、こういう行動は男子もやる。ぼくもやったことがあるし、やられたこともある。友だちと、わざと別の子の前で「アレな」とか「ほら、例のやつ」などと言ったりするのだ。「教えてくれよ」などと言う子を見て楽しむのだ。底意地の悪い遊びだ。
おそらく誰にでも経験があるだろう。大人でもやる。符丁をつくったり、自分たちの間だけに通じるあだ名をつけたりして、秘密を共有することで友情を深めることにもつながる。必ずしも悪いことではないのかもしれない。
でも目の前でやられたほうはほんとに嫌な気になるんだよねえ。著者は「女の子を傷つけるには、これくらいでじゅうぶんだ。」と書いているが、男の子も傷つく。ただ男子はやられたら「答えてくれるまでしつこく『なんのこと?』と訊きつづける」か「そのグループから離れる」のどちらかを選ぶケースが多いとおもうな。「自分がのけものにされていることを感じながらそのグループにいつづける」はあんまり選ばない気がする。
「ひとりっきりになるぐらいなら、いじめっ子グループに入っていじめられていることに気づいていないフリをするほうがマシ」と考えるのは女子のほうが多そうだ。
この本を読んでいると、女の子は幼い頃から高度なコミュニケーションをとりかわしているんだなとおもう。いい面もあり、悪い面もあるが。
「私、太ってるの」が攻撃にも自慢にも謙遜にも防衛にもなる。それらをいっぺんにおこなう高度なコミュニケーションだ。
当然ながら、「私、太ってるの」と言われたほうも、「めんどくせえな」とおもっていることはおくびにも出さずにさもびっくりしたような顔で「えっ、ぜんぜんそんなことないじゃん!」と言わなければならないのだ。たいへんだ。
男が「おれ太ってるんだよね」と言ったら文字通りの意味か冗談かのどっちかしかないし、言われたほうもハッキリと「そやな」か「『そんなことないよ』って言ってほしいんか」と言うだけだ。シンプルというか単純というか。ヒトとサルぐらいの違いがある。ぼくはサルでよかった。
『女の子どうしって、ややこしい!』では、様々な例を挙げて女の子同士の“裏攻撃”が日常茶飯事であることを示した上で、親の対応についても書いている。
子どもがいじめられていると知ったとき、特に裏攻撃を受けているとき、親が子どものためにできることはそんなに多くない。
子どもに「そんな子とは友だちでいるのをやめてください」とか「嫌なことははっきり嫌と言いなさい」なんて言うのは無駄だ。子どもが望んでいることは関係の修復であって決別ではない。いつかは「あの人と離れてよかった」とおもう日が来るがそれは今ではないし、親に言われて気づくものでもない。
学校やいじめている子の親に言いにいくのも良い結果につながらないことが多い。言って関係が改善することはまずないし、いじめられている子自身がそれを望んでいないことが大半だ。親への信頼をなくすだけ。
ではどうしたらいいのか。著者は、親が直接できることはほとんどないと主張する。子どもの話をじっくり聞く、自分の体験談を話す(ただし押し付けない)、何かやってほしいことはあれば言ってほしいと伝える、それぐらいだ。しかしそれが大事なのだと著者は説く。
基本的には子ども自身で立ち向かわなくてはならない。いじめには明確な理由がないことも多いので「いじめている子らがいじめに飽きて他のことに興味を移す」「進級や進学で環境が変わる」ぐらいしか解決方法がなかったりもする。
それでも、何も知識がなくこんなひどい目に遭っているのは世界中で自分だけとおもうよりも、世の中はこういうもので自分に原因があるわけではないと知っているほうが、ほんのちょっとは生きやすくなるだろう。
ニュースなどで語られるいじめは暴力やあからさまな嫌がらせのような“わかりやすいいじめ”ばかりだからこそ、見えにくいけどよくある“裏攻撃”について多くの事例を挙げているこの本は力になる。
その他の読書感想文は
こちら