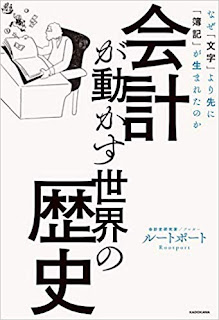文部省
昭和二十三年に文部省(現在の文科省)が中高生に向けて刊行した教科書の復刻版。
民主主義とは何か、なぜ民主主義の社会であるべきなのか、民主主義を根付かせるには何をしたらいいのか。こうしたことが丁寧に書かれている。教科書でありながらすごく重厚な本だ(刊行されたときは上下巻だったそうだ)。
昭和二十三年ということはまだ日本は独立国ではなく連合国の占領下にあった時代。
当然この教科書もGHQのチェックが入った状態で書かれたはずだ。
軍国主義の大日本帝国がこてんぱんにやられ、民主主義という新しい風が吹き込んでくる。その中で、当時の学者や官僚が若者に対してどんなことを期待をしていたのか。
この本を読むと、当時の「新しい時代の幕開け」という空気が感じられる。
当時の国の中枢にいた人たちが、いかに日本が民主主義国家として生まれ変わることに期待してひしひしと伝わってくる。
残念ながらその期待は七十年たった今もかなえられていないけれど。
七十年前に刊行された本だが、驚くほど今の世の中にあっている。
悲しいことに。
そう、ほんとに悲しい。
「七十年前はこんなことをありがたがっていたのか」と言える世の中であってほしかった。
「この頃は国民主権があたりまえじゃなかったんだねえ。政府が国民を押さえつけようとしていたなんて今では考えられないねえ」と言える世の中であってほしかった。
『民主主義』の中で「こんな世の中にしてはいけない」と書かれている社会に、今の日本はどんどん近づいている。
美しい国にしよう、国家秩序のために基本的人権を制限しよう、と叫ぶ連中が幅を利かせている。
増税や社会負担増加で今は苦しくても国家が経済的に成長すればやがては楽になる。君たち庶民もいつかはトリクルダウンにあずかれるのだから耐えなさい。
今の日本を支配しているのは、まさにここに書かれている「全体主義」そのものだ。
情報伝達手段は発達したはずなのに、資料は廃棄され、データは捏造され、公共放送機関は人事権という金玉を政府に握られ、権力者はなんとかして情報を隠そうとする。
個人的には「熱い正論をふりかざす人間」が苦手なのだが、今の世の中に欠けているのは理想論なんじゃないかとおもう。
こういうことって今、誰も言わないでしょ。
人権は大事だ、一人の生命は地球より重い、権力は弱者のためにこそ使うべきである。
そんなことあたりまえだとおもっているから誰も口にしない。
でもほんとはあたりまえじゃない。我々が享受している自由は先人たちの不断の努力によって支えられてきたもので、天からふってくるものじゃない。気を抜くと権力者によってすぐに奪われてしまうものだ。
めんどくさくてもちゃんと正論を言わなきゃいけない。
ぼくは星新一作品を読んで育ったので熱い意見に冷や水をぶっかけるような「シニカルな視点」が好きなのだが、シニカルな意見がおもしろいのは熱い議論があってこそだ。
みんなが冷や水をぶっかけてたら風邪をひいてしまう。
今って、国のトップに立つような人たちですら
「現実的に全員を救うのはムリっしょ」
「世界平和なんか達成されるわけないっしょ」
「立場がちがう人と話しあったってムダっしょ」
みたいなスタンスじゃないですか。
理想とかビジョンに興味がないし、そのことを隠そうともしない。
作家だとか落語家だとかが片頬上げながらそういうこというのはいいけど、でもそれを政治家がいったらおしまいでしょ。
「愛は地球を救う」ってのはきれいごとすぎて気持ち悪いけど、でももしかしたら愛は地球を救うんじゃねえかって気持ちも一パーセントぐらい持っておきたい。
ひょっとしたらほんとに愛が地球を救うかもしれない。そういう夢を見せてくれるのが政治家の仕事なんじゃないかとこのごろはおもっている。
この本、前半はビジョンを提示し、中盤以降は諸外国の民主主義の成り立ちや日本における政治・社会の変遷をたどることで民主主義国家の実現に向けた方法論を考察するという構成になっている。
この構成がすばらしい。ただきれいごとを語るだけではなく、過去の失敗例や外国の事例なんかがあることで具体的に考えるための手助けになっている。
GHQ検閲下にあったはずなのにアメリカの制度を手放しで褒めているわけではないのもすばらしい。
ほんとよくできた教科書だ。
よく「野党はなんでもかんでも反対してばかりだ」といって揶揄する人がいる。
ぼくは「野党はなんでもかんでも反対」でもいいとおもっている。野党が賛成ばかりになったらもうその国の民主主義は終わりだ。
自民党が下野したときも与党案に反対ばかりだった。それでいいのだ。反対意見にさらに反論することで議論が深まり、より完成度の高い法案ができる。
学生が論文を書いたら、指導教官がそれをチェックする。疑問を投げかけたり不備を指摘したり書き直しを命じたりする。
それを受けて学生は論文を書きなおす。より説得力を増した論文ができあがる。
この肯定を「教授は人の論文にケチをつけてばかりだ」といって否定する学生がいたらバカだとおもわれるだけだろう。法案も同じだ。
ぼくはこないだ「民主主義よりもっといいやりかたがあるんじゃないか?」という記事を書いた。
→
「いい独裁制」は実現可能か?
この本では、そういった反論も予想した上で、それでもやはり民主主義が最善だと結論づけている。
ぼくは二大政党制を支持していない(当然小選挙区制も)。
それは、まちがいを認めなくさせるシステムだからだ。
政治における過ちは、ミスを犯すことではない。ミスを犯したことを隠すことだ。
「過ちを隠したい」という気持ちは誰しも持っている。それはなくせない。「権力者は過ちを隠そうとする」という前提で制度の設計をするしかない。
二大政党制は、為政者のミスで政党全体の権力が失われてしまうので、政党レベルで「ミスを覆い隠そうとする」力がはたらく。
集団が全力でミスを覆い隠そうとした場合、それを暴くのは並大抵のことではない。たとえば個人の殺人はほぼ間違いなく犯人が検挙されるが「村ぐるみで一致団結して殺人を覆い隠そうとした」場合はかなりの確率で逃げおおせることができるだろう。
民主主義国家にとって必要なのは嘘がばれやすくする仕組みなのだが、二大政党制は不都合な事実を隠蔽しやすくさせる。
党内で常に権力闘争が起こっているかつての自民党の状況のほうが、むしろ健全(いちばんマシ)なんだったとつくづくおもう。
人類の歴史を見ても、権力者が他者の人権を制限してきた時代のほうがずっと長かった。
今は「
たまたま、例外的に民主主義が保たれているだけ」だ。
この本には「明治憲法の下でも民主主義国家になることはできた」と書いてある。少なくとも明治憲法をつくった人たちは国民主権の世の中にしたいという高邁な精神を持っていたはずだ。
けれど明治憲法にはいくつかの不備があり、二・二六事件などをきっかけにあっという間に軍部の暴走を許すことになった。今の日本国憲法も完璧ではない。その穴を拡げる改憲をしようと目論んでいる政治家もいる。
ちょっとしたことをきっかけに民主主義は崩されてしまうだろう。
すごくいい本だった。
今の中高生にこそ読んでほしい(まさかこれを読まれたら困ると考える為政者はいないよね?)。
しかし、戦争を経験している世代が民主主義の大切さを唱えていたのに、こういう教育を受けてきた世代が大臣や総理になったとたんに崩壊しはじめるってのはなんとも皮肉な話だよね。
教育って無力なのかもしれないと絶望的な気持ちになる。
まあ、今の二世三世大臣たちがまともに学校教育を受けていなかっただけ、という可能性も大いにありそうだけど……。
その他の読書感想文は
こちら