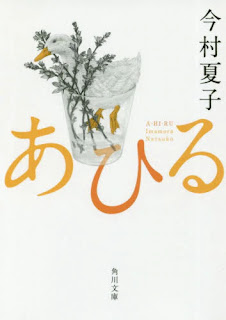SAVE THE CAT の法則
本当に売れる脚本術
ブレイク・スナイダー(著) 菊池 淳子(訳)
ハウトゥー本なんだけど、なんか妙に感動してしまった。
そうなんだ、ぼくがむずかしく考えてたことはこんなにシンプルだったんだ、と目からうろこが落ちた。
ぼくは脚本家じゃないし、脚本を書いたことなんて小学校のお楽しみ会の劇ぐらいしかないけど、これを読んで脚本を書きたくなった。ぼくにも書けるような気がしてきたぞ! よし、明日から書こう!(一行も書かない)
これは脚本にかぎらず、小説でも漫画でも物語を創作する人は読んでおいた方がいい本だ。
「おもしろい物語のテンプレート」を教えてくれる。まずはこういうシーンからスタートする。冒頭のシーンの時間はこれだけ。次はこういうシーンに……というふうに。
たしかに、おもしろい映画はたいていこのテンプレートに近い構成になっている。ハリウッドやディズニー作品はたいてい。
もちろん、このテンプレートからはずれた傑作も多い。「こんなベタな展開のストーリーを俺は書きたくない! まだ誰もやったことのない独創的な構成にするんだ!」という人もいるだろう。
でも、それでうまくいくのは、基本がきっちりできている上級者だけ。初心者は基本に従って書く方がだんぜん楽だ。
野球初心者がトルネード投法や振り子打法を試しても成功するはずがない。ああいう変則的な技を使いこなせるのは、基本を完璧に身につけた上級者だけなのだ。
物語を完成させたことがないけど書きたい人は、まずはこのテンプレートに従って書くべき。まちがいない。
書かれていることは、すごく合理的だ。
「まず自分が書きたいテーマと向き合おう」「自信の内面を掘り下げよう」みたいな抽象的なアドバイスは一切ない。
きわめてロジカルに、手取り足取り脚本の書きかたを教えてくれる。
成功している脚本のパターンを分類し、どういった要素から構成されているかを説明。
なぜその要素が必要なのか、何をしたらいいのか・いけないのか、失敗しがちなポイントはどこなのか、有名な映画タイトルを出しながら懇切丁寧に教えてくれる(ただぼくはあんまり映画を観ないので半分もわからなかったけど)。
恥ずかしながらぼくも学生時代、小説を書いたことがある。最後まで到達しなかったものがほとんどだし、完成させたものもまったく満足のいくものではなかった。賞に応募したこともあるが箸にも棒にも掛からなかった。あたりまえだ。自分ですら満足していないのに他人を楽しませられるはずがない。
おもえば、ぼくがやっていたのは「料理の完成品を見て、同じ料理を作ろうとする」ようなものだった。
何千冊も小説を読んだのだから自分にも書けるとおもっていた。「何千回も料理を食べたことがあるのだから自分も料理人になれる」とおもうように。今からおもうととんでもない話だ。
やるべきは、料理を食べることではなく、レシピを読むことだったのだ。
プロが書いた工程を読み、最初に材料を全部そろえ、レシピ通りの工程・分量で作業する。勝手なアレンジをくわえなければ大きく失敗しない。
映画ってたくさんの人がかかわってるしすごい額のお金が動くから複雑なものだとおもってしまいがちだけど、じつはシンプルなものなのだ。
たしかに名作映画のストーリーは、短い文章で表現できる。
「タイムマシンで過去に行き歴史を変えずに戻ってこようとする」とか
「家にひとり取り残された少年が泥棒を撃退する」とか
「新しいおもちゃに主役の座を奪われたカウボーイ人形が、新しいおもちゃといっしょに持ち主のもとに戻る冒険をする」
とか。
小説を原作にした映画があるけど、長篇小説を映画化するとたいてい失敗する。文字のほうが情報の密度は濃いので、映画にちょうどいいのは短篇か中篇ぐらいだ。
たとえば『ショーシャンクの空に』の原作『刑務所のリタ・ヘイワース』は中篇。『鉄道員』は短篇。
短篇や中篇小説にはあれもこれも詰めこんでもわかりづらくなるだけだ。映画脚本はワン・アイデアを肉付けしていくぐらいでいいのだろう。
くりかえすけど、ストーリーをつむぎたいとおもっている人にとっては読んでおいて損はない本。
ああ、あと二十年早くこの本に出会っていたらなあ。そしたらぼくは今頃売れっ子作家まちがいなしだったのに(この発想がもうダメだ)。
その他の読書感想文はこちら